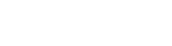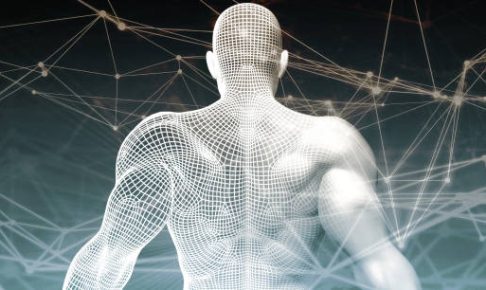腰痛だけでなく関節痛、膝痛、背部痛、頭痛、生理痛などの症状で、多くの方が服用される「痛み止め」のお薬ですが、皆さんはこのお薬が体の中でどのような箇所に作用し、どのような効果で痛みを感じなくなるのかをご存知でしょうか?
今回は「痛み止め」の本当の働きをテーマに、特に腰痛時のお薬との付き合い方をお話したいと思います。
薬でどうして痛みがなくなるのか
皆さんが一度は服用されたことがある「痛み止め」。頭痛持ちの方などは日頃からよく服用しているかもしれません。
病院で処方されたり、ドラッグストアなどで販売されている「痛み止め」のお薬のほとんどが、『NSAIDs(エヌセイズ:非ステロイド性消炎鎮痛薬)』といわれる種類のお薬で、ステロイド以外の抗炎症作用、鎮痛作用、解熱作用を持つ薬剤の総称です。
NSAIDsには多くの種類があります。
- アスピリン(バファリン®など)
- ロキソプロフェン(ロキソニン®など)
- ジクロフェナク(ボルタレン®など)
- インドメタシン(インダシン®など)
- メフェナム酸(ポンタール®など)
- スルピリン(メチロン®など)
- アセトアミノフェン(アンヒバ®、カロナール®など)
- その他
- アスピリン(バファリンA®など)
- イブプロフェン(イブ®など)
- エテンザミド(ノーシン®,新セデス®など)
- イソプロピルアンチピリン(セデス・ハイ®など)
- アセトアミノフェン(タイレノール®、小児用バファリン®など多くの市販薬)
- その他
聞いたことがある名前や購入したことのあるお薬の名前が多く出てきていると思います。これら全てがNSAIDsと呼ばれるお薬になります。
薬局に行って簡単に手に入ってしまう「痛み止め」ですが、意外とその作用が起こる仕組みや副作用について知らない人も多いのではないでしょうか?
では、このNSAIDsの作用について解説していきたいと思いますが
そもそも痛みとはどのように感じているのか、まずはそこから説明します。
痛みの情報を脳へ伝達する物質「プロスタグランジン」
私たちが痛みを感じる際、体の中では様々な物質が生成され、その情報が脳へと送られます。その物質の中で最も痛みと関連しているのが「プロスタグランジン」です。
- 血圧低下作用
- 血小板凝集作用
- 睡眠誘発作用
- 動脈管開存作用
- 子宮収縮作用
- 平滑筋収縮作用
- 末梢血管拡張作用
- 発熱・痛覚伝達作用
- 骨新生・骨吸収作用
- 胃酸分泌抑制
- 胃粘膜保護
などがあります。
プロスタグランジンが多く生成される症状としては、組織の損傷、ぎっくり腰や寝違えなどの炎症が起きている時になります。
体の中で炎症が起きると、細胞膜のリン脂質が分解され、アラキドン酸を経てプロスタグランジンが生成されます。この流れをアラキドン酸カスケードと言います。
そして、プロスタグランジンには痛みの感じ方を敏感にする作用や、痛覚伝達作用があるため、少し動いただけでも激痛が走ったり、熱っぽくなったりしてしまいます。
少し分かり易くするために下に流れを書きます。
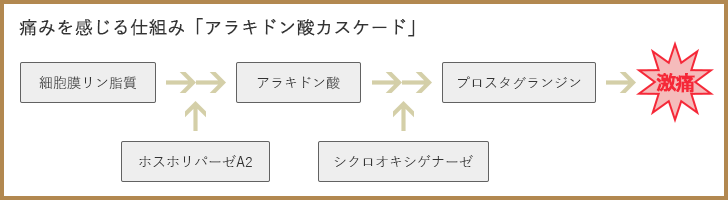
となります。
つまり、プロスタグランジンが痛みの原因なのであれば、そのプロスタグランジンを生成できないようにすればいい。そこで作られたお薬がNSAIDsになります。
NSAIDsの働きは、アラキドン酸カスケードの中のシクロオキシゲナーゼに作用し、その働きを抑制します。
シクロオキシゲナーゼの働きを抑えることにより、アラキドン酸からプロスタグランジンが生成される流れが断ち切られ、痛みの原因となるプロスタグランジンが生成されず、痛みを感じなくなるわけです。
分かり易く書きますと、
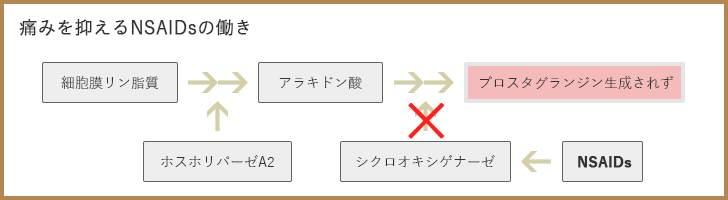
となります。
こうしてNSAIDsは痛みを感じなくさせる素晴らしい作用がありますが、もちろん副作用もあります。次はその副作用についてご説明いたします。
NSAIDsの副作用
プロスタグランジンの生成を抑えることになるので、プロスタグランジンの痛み以外の多くの働きを抑え込むことになってしまいます。その結果、多くの副作用が出てきてしまいます。
胃腸障害
プロスタグランジンには胃酸分泌抑制、胃粘膜保護の作用があるため、NSAIDsによって生成を抑制されると、胃腸の粘膜が傷つき易くなり、胃潰瘍になる恐れもあります。
経口投与時には、NSAIDsが胃粘膜に直接接触することでの局所刺激も起こしてしまいます。一緒に胃薬を服用することで、抑えることができます。
アスピリン不耐(過敏)症
アスピリンやその他のNSAIDsに過敏で、血管浮腫、全身性じんま疹、気管支喘息、咽頭浮腫、ショックなどのさまざまな症状を示す場合があります。アスピリン不耐(過敏)症の症状はアナフィラキシーとも類似していますが、免疫反応ではなくシクロオキシゲナーゼの阻害が関わっていると考えられています。
- 腎機能障害
- 肝機能障害
- 血小板、心血管系障害
これらの副作用のことも忘れずに、過剰な服用にはお気をつけください。
今回は、「痛み止め」とは一体どんなものなのかを皆さんに知っていただくための記事を書きましたが、次回は「痛み止め」のお薬の役割と根本的改善とはどのような違いがあるのかをお伝えさせていただきます。